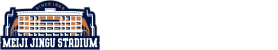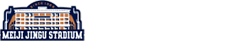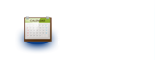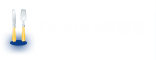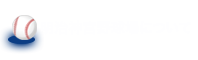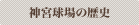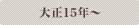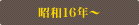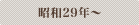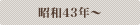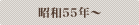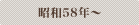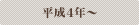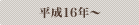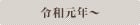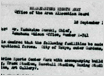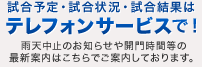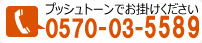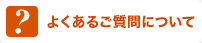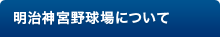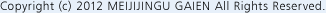昭和16年(1941)
12月8日 太平洋戦争勃発
昭和18年(1943)
4月7日 文部省から東京六大学野球リーグ解散の通達
4月28日、東京六大学野球連盟は解散し、リーグ戦は正式に中止となりました。そして、早大・安部球場(当時は戸塚球場)にて学徒壮行早慶戦(10/16)が行われ、この壮行試合が戦時中最後のものとなり昭和19年学生野球は全面中止になりました。
昭和20年(1945)
5月25日 空襲により球場大火災
当時、神宮球場は東京都の貯蔵倉庫として使用されていました。空襲により投下された数百個の焼夷弾に、格納されていた薪炭、建築資材、糧まつなどが数日間燃え続け、手のほどこしようもありませんでした。火の勢いでアーケードの鉄扉や窓枠などは溶解し、鉄筋コンクリート造りの巨体も僅かに鉄骨の残がいが残るという惨状でした。
9月18日 明治神宮外苑、進駐軍に接収
空襲で無残な姿をさらしていた神宮球場は『ステートサイド・パーク』と名付けられ、進駐軍専用野球場として使用される事になりました。昭和21年5月から22年6月にかけて修復工事を行い、8基の照明塔が新設されました。
10月28日 東京六大学OB紅白試合(紅3-11白)
11月18日 オール早慶戦(延長11回、早大3-6慶大)
観衆は45,000人にものぼり、この試合は敗戦によって虚脱状態にあった日本人の心を奮い立たせるとともに、翌21年3月11日の東京六大学野球連盟の復活へとつながっていきました。
11月23日 神宮球場で初のプロ野球、東西対抗戦(東軍13-9西軍)
東軍(巨人・名古屋・セネタース)
西軍(阪神・阪急・近畿・朝日)
昭和21年(1946)
3月11日 東京六大学野球連盟復活(総当たり1回戦制)
神宮球場は接収されたままで使用許可がおりないため、後楽園・上井草などの球場を併用して試合を行いました。
9月14日 進駐軍、シーズンオフでの学生野球使用を許可
昭和25年秋季リーグ戦より、全試合に開放されました。
昭和23年(1948)
4月17日 東京六大学春季リーグ戦入場式
東京六大学野球リーグ戦を他球場と併用して行いました。神宮球場の使用試合数は、春季24回・秋季33回でした。
8月28日 プロ野球公式戦 巨人-急映(東映)
進駐軍新聞スターズ・アンド・ストライプス主催により、プロ野球巨人対急映の試合を進駐軍が設置した照明設備を使用して、東京では初のナイターで行われました。
11月13日 大学野球王座決定戦
東京六大学・東都大学・関西六大学野球連盟の秋季優勝チームが1回戦総当りで試合を行いました(法大優勝) 。これが、昭和27年から始まる全日本大学野球選手権大会に発展していく礎となりました。
昭和24年(1949)
10月17日 サンフランシスコ・シールズ来日
昭和9年のベーブ・ルース以来の日米親善試合で全日本と対戦しました。この来日により刺激された日本プロ野球界には新興チームが続出し、翌25年にセ・パ両リーグが分裂する発端となりました。
昭和25年(1950)
11月22日 神宮球場初のプロ野球日本選手権(毎日オリオンズ-松竹ロビンス)
パ・リーグの毎日が、セ・リーグの松竹を4勝2敗で下して優勝しました。神宮球場で行われたのは第1試合のみで第2試合以降は後楽園・甲子園・西宮・中日・大阪で行われました。
昭和26年(1951)
11月10日 米大リーグ選抜チーム来日
総監督はフランク・オドール、監督は米プロ野球界においてベーブ・ルースやゲーリックと並ぶ強打者として有名なディマジオ率いる米大リーグ選抜軍でした。パーネル、シャンツ等の投手陣が好投して日本のプロ野球は対抗できず通算成績は1勝13敗2引分けに終わり、神宮球場では3試合が行われました。
11/10 米3-2 全セ、11/11 米12-0全日本、11/19 米5-5巨人軍
昭和27年(1952)
6月 軟式球場(青山口西側)
接収中の中央広場には、進駐軍によってソフトボール場を始め、さまざまなスポーツ施設が作られていました。進駐軍が残したこれらのスポーツ施設を利用して軟式球場を仮設し、のちに全6面の軟式球場となりました。
8月22日 第1回全日本大学野球選手権大会
各地区連盟代表8チームの3日間にわたる熱戦の結果、東京六大学野球連盟代表の慶大が優勝しました。